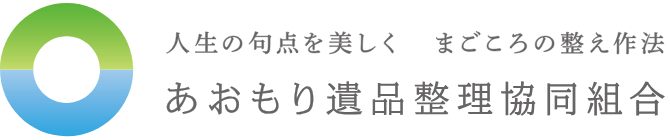母が残した時間 〜弘前での遺品整理を通じて感じたこと〜
北海道からご依頼いただいた70代のご主人。弘前市のご実家で、去年の春に亡くなられたお母さんの遺品整理のご相談でした。
一人暮らしをされていたお母さんは、病院で静かに眠るように息を引き取られたとのこと。ご依頼の電話口での、そっと抑えられた悲しみが今も心に残っています。
写真を見ていただければわかるように、ご依頼当初、お部屋は衣類や日用品で溢れかえっていました。段ボール箱や青いプラスチックケース、洋服ラックには色とりどりの衣装がぎっしりと詰められていて、一見すると「片付けられていないお部屋」に見えるかもしれません。しかし、作業を進めるうちに、私たちはあることに気づきました。
それは、このお部屋全体が、一人の丁寧な女性の人生そのものだったということです。
丁寧に大切にされてきた品々たち
お母さんの衣類を一つひとつ見ていくと、どれもが大切に保管されていました。季節ごとに分類された洋服たち。色合いを考えて選ばれたであろう装い。年月とともに流行は変わっても、上質さと清潔感を失わない、そういう美学を感じました。クローゼットの中、タンスの中、どこを見ても、ご自身の人生を大事にしようとする姿勢が伝わってきたのです。
「母は整理整頓が得意で、本当にきれい好きな人でした」
作業が進む中で、ご依頼者さんがぽつりとおっしゃった言葉です。その瞬間、私たちが感じていた違和感が腑に落ちました。これは「片付けられていない部屋」ではなく、「丁寧に大切にされてきた物たちの集積」だったのです。
やや増えてしまった荷物も、決して無秩序ではなく、何か理由があったのかもしれません。一人暮らしの長さ。健康を失う前の不安感。あるいは、人生で大切にしてきた品々を、手放すことへの葛藤。そうしたお母さんの心の声が、この空間に静かに満ちていたのではないでしょうか。
核家族化という時代の波の中で
作業を進めながら、私たちが何度も考えたことがあります。それは、本来ならば、こうした遺品整理は家族で、思い出を語り合いながら、時間をかけて行うものだったということです。
「これは母が好きだった帯だ」
「このお皿は、私たちが子どもの頃、いつも使っていた」
「この衣装は、父がまだ生きていた頃に買ってもらったものかな」
そうした会話の中で、人は改めて親を知り、自分たちのルーツを感じることができたはずです。品物を通じて、失った人とあらためて向き合う。そして、心の中で別れを告げる。本来のお葬式と同じくらい大切な、故人との最後の時間。
しかし、現代社会はそれを許してくれません。遠く離れて暮らす子ども世代。仕事の都合。時間の制約。そして、故人が一人暮らしを選んだがゆえの距離感。こうした現実の中で、多くのご遺族が、私たちのような業者に託すしか選択肢を持たないのです。
静寂に満ちた新しい時間へ
作業の最後、お部屋が本来の姿を取り戻した時、そこには静寂がありました。
青々とした壁。整然と並んだ畳。大きな窓から入る光。何もかもが片付いた空間は、同時に、お母さんの存在が遠くなったことを物語っていました。
ご依頼者さんは、仕上がったお部屋の写真を見ながら、何か言い仕度そうでしたが、言葉にならなかったのでしょう。その表情に、私たちが預かった以上の重さを感じました。
母と子。遠距離。時間の経過。そして、見送られ方。
遺品整理という仕事を通じて、私たちが本当に預かっているのは、物ではなく、誰かの人生の物語なのだと、改めて感じるのです。
お母さんが残してくれたこのお部屋が今、静かに別の時間を迎えようとしています。